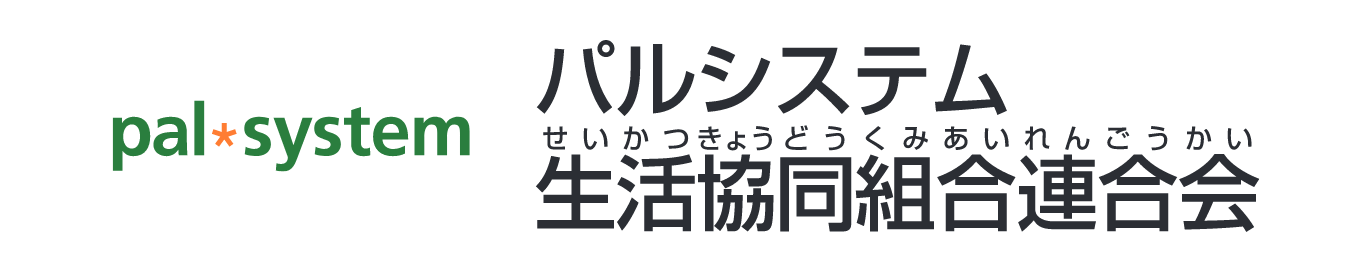
有機野菜には安全・安心なイメージがあるけれど、本当はどんな野菜なんだろう? 有機栽培の野菜づくりを産直産地(※)と長年取り組んでいるパルシステムに教えてもらいました。
※産直産地=パルシステムの産直の考え方を理解し産直協定を結んだ産地(2021年6月で国内外、農林水産業389カ所)。
- 生活協同組合の仕事
- 安全な野菜づくりの仕事
- 環境にやさしい仕事
生物や自然環境に安全で負荷もかけない栽培内容と、厳しい基準(有機JAS[ジャス]認証)をクリアした野菜だよ!
「有機野菜」を名乗るためにクリアすべきこと

化学合成農薬、化学肥料を使用しない「有機(オーガニック)野菜」。ただし、「これは有機野菜です」と名乗るには、法律や生産の基準をクリアして、検査で認められなければなりません。
1法律をクリア
1999年に改正された「JAS法」に基づき、有機農産物の検査・認証制度が新たに導入され(2001年施行)、それにより「有機(オーガニック)野菜」と表示できる農産物や有機農業の方法が定められています。
2生産の基準をクリア
有機農産物は「有機農産物の日本農林規格」(有機JAS規格)の基準に従って生産されなければなりません。
主な基準
-

耕地は、播種(種まき)または定植(植え付け)の2年以上前から、 化学合成農薬、化学肥料を使っていない。
-

栽培中、化学合成農薬、化学肥料を使用しない。
-

周辺から農薬が流入しないようにしている。

※農薬はやむを得ない場合に限り、天然の物質または化学的処理を行っていない天然物質由来のものの使用が認められています。
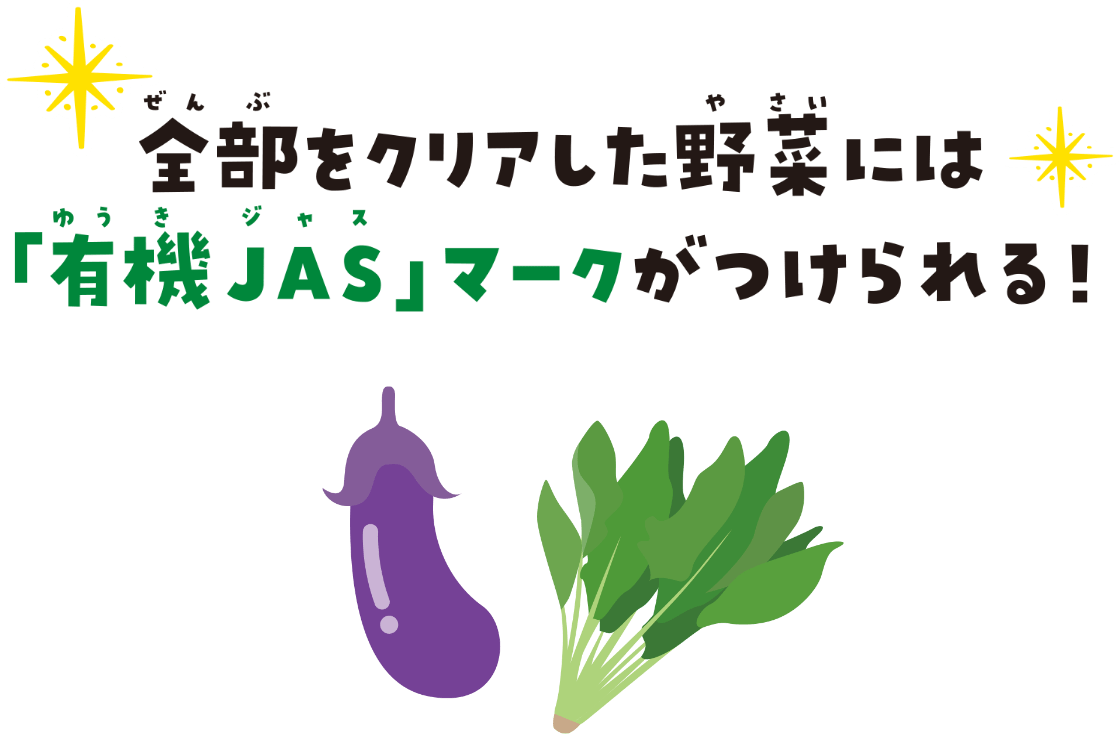
❶の法律や❷の基準をクリアし、耕地や農産物が登録認証機関の検査で認証されると、商品に「有機JAS」マークをつけることができます。
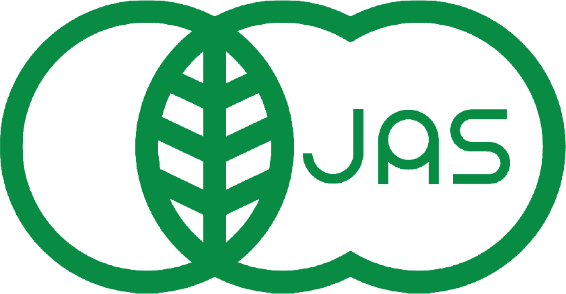
▲有機JASマークは厳しい法律や基準をクリアした証し!
パルシステムは青果に独自の基準があって、有機JAS認証されたものは「コア・フード」というケモ!

◀︎「コア・フード」のシンボルマークは
益虫のテントウムシ

カタログや野菜には「有機JAS」と「コア・フード」のマークがついているケモ。

パルシステムと有機農産物

有機農産物を育てることは簡単ではありません。化学合成農薬や化学肥料に頼らない農業は、技術が必要なほかにも大変手間がかかり、断念する生産者もいます。実際、有機JASの認証を取得した耕地面積は、日本の全耕地面積の0.2%程度です(農林水産省2020年)。
パルシステムは認証制度が作られる前の1980年頃から産地と取り組み、2020年は全国66産地、1192ha(ヘクタール/有機JAS認証耕地面積の約9.9%)で栽培しています。

▲パルシステムの「有機野菜セット」。旬の有機野菜がセットで届く
有機野菜には
生産者の工夫や努力が必要
健康な土づくりや害虫対策、そして、雑草対策が欠かせません。除草機械が入らないところは手作業で行います。

▲有機栽培の玉ねぎ畑で雑草を手で除草する生産者
有機野菜には
組合員(利用者)の理解と買い支えが大切
40年を超える「産地交流」で、組合員(利用者)と「顔の見える関係」を築き、相互理解や信頼を深め、利用につなげています。

▲産地交流の様子。2021年度はオンラインなどで4167人が交流
フードロス削減の努力もしています
パルシステム生活協同組合連合会
産直事業本部 野菜課 鉢木正明さん
例えば品質不良などを見越して仕入れた「予備野菜」は、子ども食堂やフードバンクなどの生活困窮支援に年間20万食分提供しています。また、豊作などで産地で余った野菜は、「もったいないグリーンセット」として組合員(利用者)に利用してもらうことで、できるだけ無駄が出ないようにしています。
生産者が大事に育てた野菜なので、捨てられることのないようにしたいです。

▲「もったいないグリーンセット」


























